Hej!スウェディッシュヌードラーです。
日本に過去最大級の台風が迫っていますね。心配だな、、、
特に関東の皆さん、用心に用心を重ねてください。
さあ、このブログだいぶ御沙汰してしまって、自己反省中です、、、
シェアしたいことはあっても、9月の新学期に入ってから、平日があまりにもハードすぎて落ち着いてブログを書いている時間なんぞありませんでした 🙁
それに、思春期かっ!というぐらいニキビに悩まされています。。。
さて、スウェーデンはWinter has come状態です。まだ10月なのに!
こちらをご覧ください。。。
10月6日(日)


さみーです。スウェーデン、いよいよ本気と本性出してきました。
9月5日(木)

日照時間も、ひと月前と比べると2時間以上短くなっているって衝撃です。
流石にヒートテックを着始めました。
、、、と思ったら今週は、少しだけ暖かくなりました。だからエアリズム!二桁になると暖かいと感じる感覚、北欧ならではです。
10月11日(金)

さて、今日はスウェーデンにおける移民とことば、特に母語教育についてシェアしたいと思います。
僕は基本的に毎日複数の小学校でフィールドワークをしているのですが、その小学校は社会経済的に低い層の人たちが暮らす地区にあります。そのうちのひとつの学校については、いわゆるスウェーデン人もいるのですが、ほとんどが移民・難民を背景に持つ家庭の子どもで、出身国籍もさまざまです。そして、驚くことに非スウェーデンルーツの割合は98%です。
そのため、かれらの母語はスウェーデン語ではないケースが多く、母語教育を受けている児童が多くいます。
|
【スウェーデンの母語教育】 スウェーデン語が母語ではない児童生徒には、自身の母語教育を受ける権利があります。自治体にもよりますが、学校に5人以上同一母語の児童生徒が在籍していれば、通学する学校で母語教育を受けられるケースが多いです。5人未満の場合は、学校外もしくは放課後に学校内の施設で母語教育がなされているケースが多いようです。ただし、強制されるものではなく、任意での参加です。 Skolverket(学校庁)の2018年のデータによると、2016年10月時点で、母語教育を受ける権利のある全児童生徒数は、275,329人で、そのうちの上位2言語は、アラビア語(64,261人)とソマリア語(20,661人)でした。 <出典>Skolverket (2018) Beskrivande data 2017: Förskola skola och vuxenutbildning. (最終アクセス:10月11日 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3953). |
僕が見ている学校の1つでは、まさにアラビア語とソマリア語の母語教育がなされています。放課後等に実施されるわけではなく、時間割のなかに「Mödersmål(=Mother tongue=母語)」として組み込まれています。(もうひとつの学校では、他言語の母語教育もなされています!)
該当する2言語以外が母語の子どもたちは、代わりにスウェーデン語の授業を受けたり、自習をしたりしていました。
母語教育の教員に関しては、学校が雇用した当該言語話者で、教員免許を持った人もいれば、そうでないケースもあります。
授業内容は、コミュニケーションを重視したものというより、文字として書けるようになることに重きが置かれているような印象です。というのも、かれらは、家庭では母語を使って会話している時間がほとんどなので、「話す」という意味でのコミュニケーションスキルはすでに持ち合わせているからだと思われます。
学校と家庭で、このような言語教育環境に置かれているので、かれらはデフォルトでバイリンガル、もっと学年が上がれば英語も流暢に話し始めるので、トリリンガルになります。
自身も移民や難民としてスウェーデンに来た、もしくは移民・難民として来た両親のもとに国内で生まれたかれらは、低い社会経済的背景をはじめ、さまざまな理由から社会において上昇できないケースが見られます。
しかし、かれらには言語という大きな武器があります。もちろん、言語はただのツールでしかないという見方もありますが、そのツールが上手く活用されれば、最強の武器になるのではないでしょうか。母国とスウェーデンをつなぐ存在にだってなれるし、次世代へのロールモデルという大きな役割も果たせるかもしれません。
今回は、かなり簡単ではありましたが、スウェーデンの母語教育から、移民とことばを考えてみました。
僕の研究自体は母語教育そのものではないですが、大きく関わる要素の1つなのでもっともっと観察し、話を聞いていきたいと思います。
あまり研究進捗は芳しくありませんが、頑張りまーす。
それでは、Hej då!
後記:今週はフィールドワークストップウィークで、毎日大学のオフィスにいたので、キャンパス内のレストランでランチしました。トップ画像は、研究の供・三銃士です。
月曜日!牛肉!

火曜日!鮭!

木曜日!パエリア!

金曜日!サカナ!

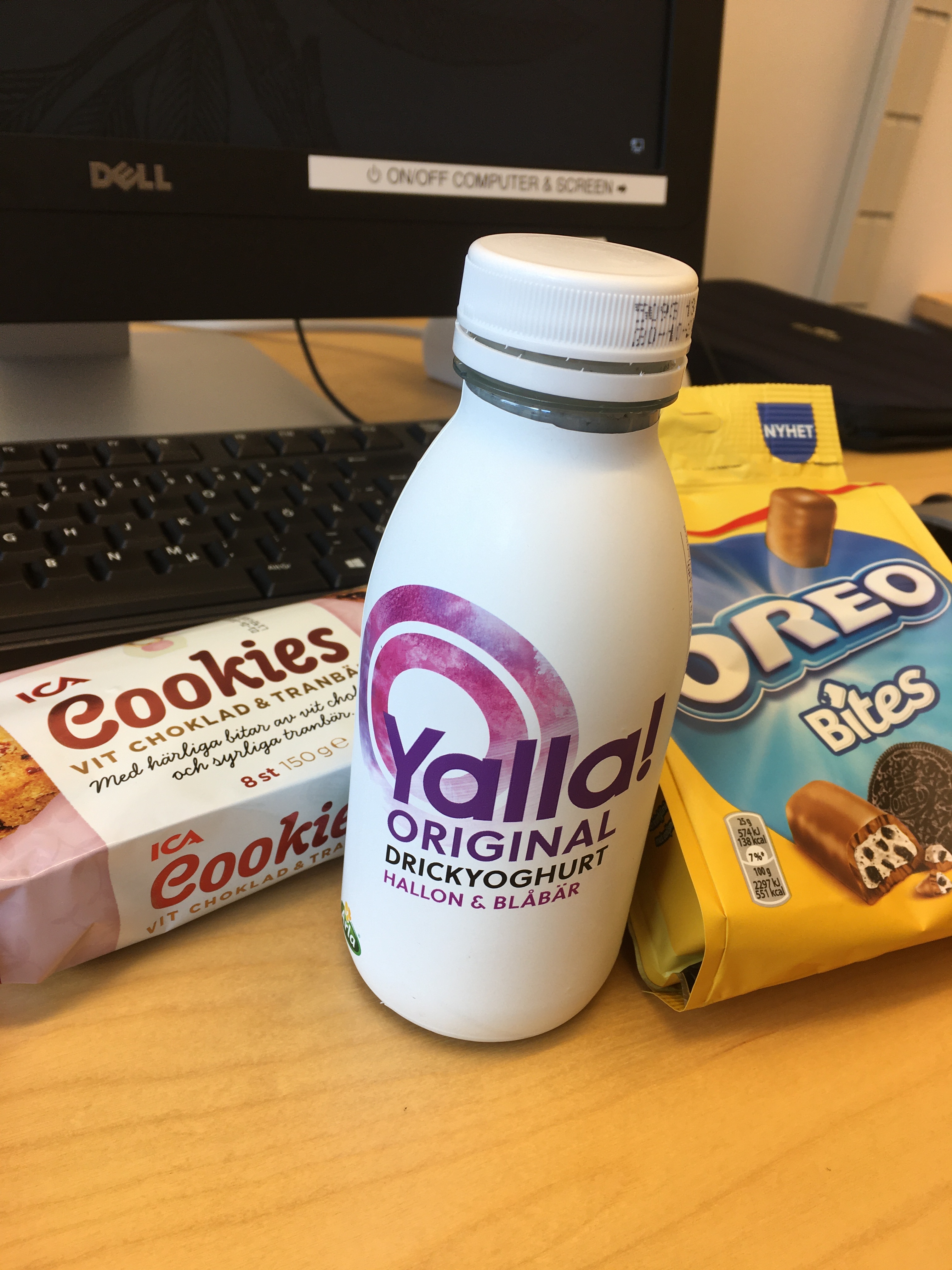


コメント